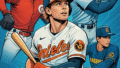この記事にはアフィリエイト広告を掲載しています
「将来、お金に困らない人生を送りたい」
「できれば会社に縛られず、もっと自由に生きてみたい」
でも、現実は、毎月の支払いに追われ、貯金も増えない日々…
そんな葛藤を抱えていた私がお金の勉強を始めたきっかけとなったのが『金持ち父さん 貧乏父さん』でした。
こんにちは、Chanです。
今回はこのベストセラーを内容に沿って紹介し、本書を読んで私が気づいた「お金の本質」や実生活での変化についてレビューをしていきます。
※この記事では本の内容を要約していますので一部ネタバレを含みます。
ご了承いただける方はぜひ最後までお読みください。
お金について学校で教わらなかったこと

「なぜ一生懸命働いているのにお金が貯まらないのか?」
「なぜお金持ちはますますお金持ちになるのか?」
こうした疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。
現代社会では多くの人がお金に関する悩みを抱えているにもかかわらず、学校では税金や投資の基本すら教えてくれません。
1997年に出版されたロバート・キヨサキ氏の書籍『金持ち父さん・貧乏父さん』は世界中で5000万部以上を売り上げる大ベストセラーとなり、多くの人の「お金に対する考え方」を根本から変えました。
物価高や増税、年金不安が広がる2025年、私たちは改めてこの名著から多くの学びを得ることができるのではないでしょうか。
この本をおすすめしたい方

- お金に対する漠然とした不安がある方
- 投資や副業に興味はあるけど、一歩踏み出せない方
- 家計管理をもっと賢く行いたいと考えている方
- 子どもに「本当の金融教育」をしたい子持ちの方
本書は単なる「お金のハウトゥー本」ではなく、「お金とどう付き合っていくか」という人生哲学とも言える一冊です。
ロバート・キヨサキ氏が伝えたかった真実
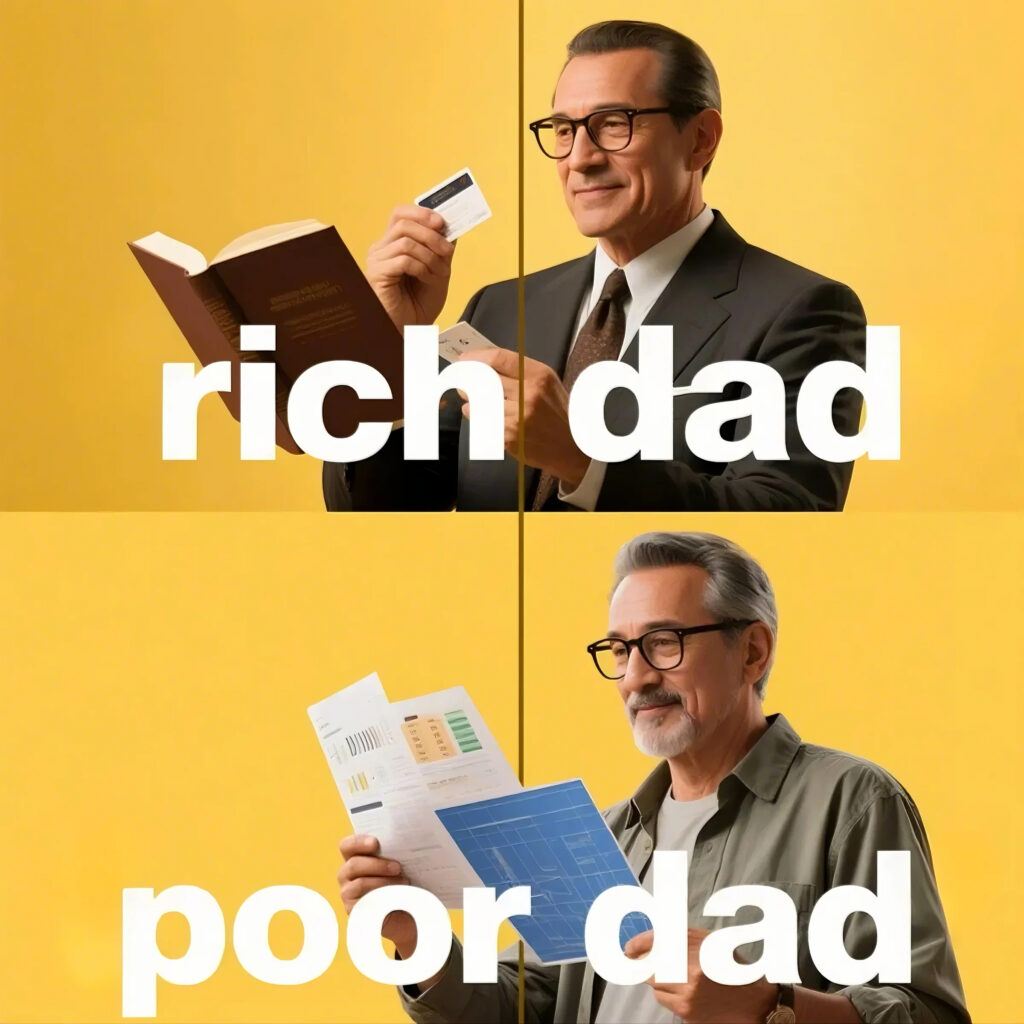
著者のロバート・キヨサキ氏は、ハワイ出身の日系4世であり、起業家・投資家として成功を収めた人物です。
本書は彼自身の実体験に基づき「金持ち父さん」と「貧乏父さん」という対照的な2人の父親から学んだ教訓を中心に構成されています。
この2人の価値観やお金に対する考え方の違いを通じて「なぜ学歴が高く、まじめに働いていてもお金持ちになれないのか?」という問題を浮き彫りにします。
初版から25年以上が経過した今も本書が読み継がれているのは、そこに時代や地域を超えた普遍的な価値があるからしょう。
特に、終身雇用制度が崩れ、個人が自らの将来に責任を持たなければならない現代において本書の教えはますます重要性を増しています。
お金に対する考え方が180度変わる 金持ち父さんの6つの教え

キヨサキ氏は金持ち父さんから受けた「6つの教え」以下のように述べています。
資産と負債の違いを理解する
本書で最も衝撃的な教えの一つが、資産と負債の定義です。
多くの人が「マイホーム」「車」などを「資産」と捉えがちですが、キヨサキ氏はこう定義します。
資産とは、私のポケットにお金を入れてくれるもの。負債とは、私のポケットからお金を取っていくもの
この定義に従えば、住宅ローンを組んで購入したマイホームは、維持費や返済、固定資産税などがかかるため「負債」となります。
一方で、家賃収入を生む投資用不動産や配当を生む株式などは「資産」です。
この考え方の転換こそが、資産形成の第一歩と言えるのではないでしょうか。
- 持っているとお金を増やしてくれるもの→資産
- 持っているとお金を奪っていくもの→負債
「お金のために働く」から「お金に働かせる」へ
貧乏父さんは「いい学校に行き、いい会社に入って、安定した給料をもらうように」と教えました。
一方、金持ち父さんは「お金のために働くのではなく、お金を自分のために働かせなさい」と説きます。
本書で紹介される「ラットレース」という概念はいくら収入が増えても、支出も増え、結果的にずっと働き続けなければならない状態を表しています。
このラットレースから抜け出すには労働収入だけでなく、不労所得(パッシブインカム)を得ることが鍵となると述べています。
現在では不労所得を得る手段が多様化していて、お金を働かせる仕組みが溢れている状態と言えます。
- 株式投資による配当金
- YouTubeなどの広告収入
- アフィリエイト
あなたにできそうな不労所得への第一歩はどれでしょうか?
お金に働いてもらうことは、「ラットレース」から抜け出すための第一歩となる。
マネーリテラシーの重要性
金持ち父さんが最も強調したのが「マネーリテラシー」、つまりお金に関する知識と理解力です。
会計・投資・法律・税金という4つの基本分野を学ぶことが、経済的自由への第一歩とされています。
では、なぜ学校ではお金についての教育をしてくれないのでしょうか?
キヨサキ氏はこう指摘します。
「学校教育は従順な労働者を育てるためのものであり、起業家や投資家を育てるものではない」
現在は、YouTube、書籍、オンライン講座やセミナーなど誰でも手軽に金融教育にアクセスできる時代となり、お金の勉強をするためのハードルはかなり下がりました。
現在の教育環境を活かして、税金の仕組みや社会保障、投資に関して常にアップデートを続けることが求められます。
YouTubeで無料でお金のことが学べる時代。あなたはどんなチャンネルで学んでいますか?
- マネーリテラシーを高めると経済的自由に近づくことができる
- お金の勉強をするためのハードルが下がり、マネーリテラシーを高めるための環境が整ってきている
起業家精神と投資家マインド
キヨサキ氏は人々をキャッシュフロー・クワドランドという次の4つに分類しています。
※「キャッシュフロー(お金の流れ)」と「クワドランド(4分割)」を組み合わせた造語
- E(Employee/従業員):企業に雇用され、給与所得を得る
- S(Self-employed/自営業者):自分の商品やサービスを提供して、収入を得る
- B(Business owner/ビジネスオーナー):仕組みや人に働いてもらい、収入を得る
- I(Investor/投資家):お金に働いてもらい、そこから収入を得る
キャッシュフロー・クワドランド
| 労働収入 | 権利収入 |
| 雇われて働いている E (従業員) | 他人やシステムに働いてもらう B(ビジネスオーナー) |
| 自分で自分を雇っている S (自営業) | お金を働かせて収入を得る I (投資家) |
左右の違いは、左側のEとSは自分自身の時間や労働力の対価として収入を得ているのに対して、右側のBとIは他人や仕組み、お金が働いてくれて収入を得ているということです。
多くの人がEやSに留まる中で、真の経済的自由を得るにはBやIを目指す必要があるとキヨサキ氏は述べています。
しかし、それぞれの区分にはメリット・デメリットがあります。
| 区分 | メリット | デメリット |
| E | 安定した収入・福利厚生がある | 収入が時間や労力に依存しやすい 昇給に限界がある 自由な時間が少ない |
| S | スキルを直接活かせる 働き方や時間を決めやすい 努力次第で収入を増やせる | 休むと収入が減る 自分でこなす範囲が広く多忙 |
| B | 仕組みで収入を生み出せる 大きな収入を得る可能性がある | 初期投資が大きい 人材育成・管理が難しい 事業失敗のリスクがある |
| I | お金が働く仕組みを作れる 大きなリターンの可能性がある | 資産を失うリスクがある 専門知識と分析力が必要 市場変動の影響を強く受ける |
重要なのは、「安定した給料」こそが安全だと思うのではなく、「収入源を一つに絞ることはリスクである」と認識することです。
まずは、EからSに移るための副業から始めるのも一つの手でしょう。
学び続けることの重要性
金持ち父さんは「お金持ちは一生学び続ける」と語ります。
いくら学校の成績が良くても、社会に出てから学びを止めた人は資産を築けません。
- 投資についての学び
- 時代の変化を読み取る力
- 税制や法律の知識
これらを継続的に学びアップデートすることで、資産形成が可能になるのです。
まずは1ヶ月に1冊、マネー本を読むことを始めてみてはいかがでしょうか。
誤解しやすいポイントと注意点
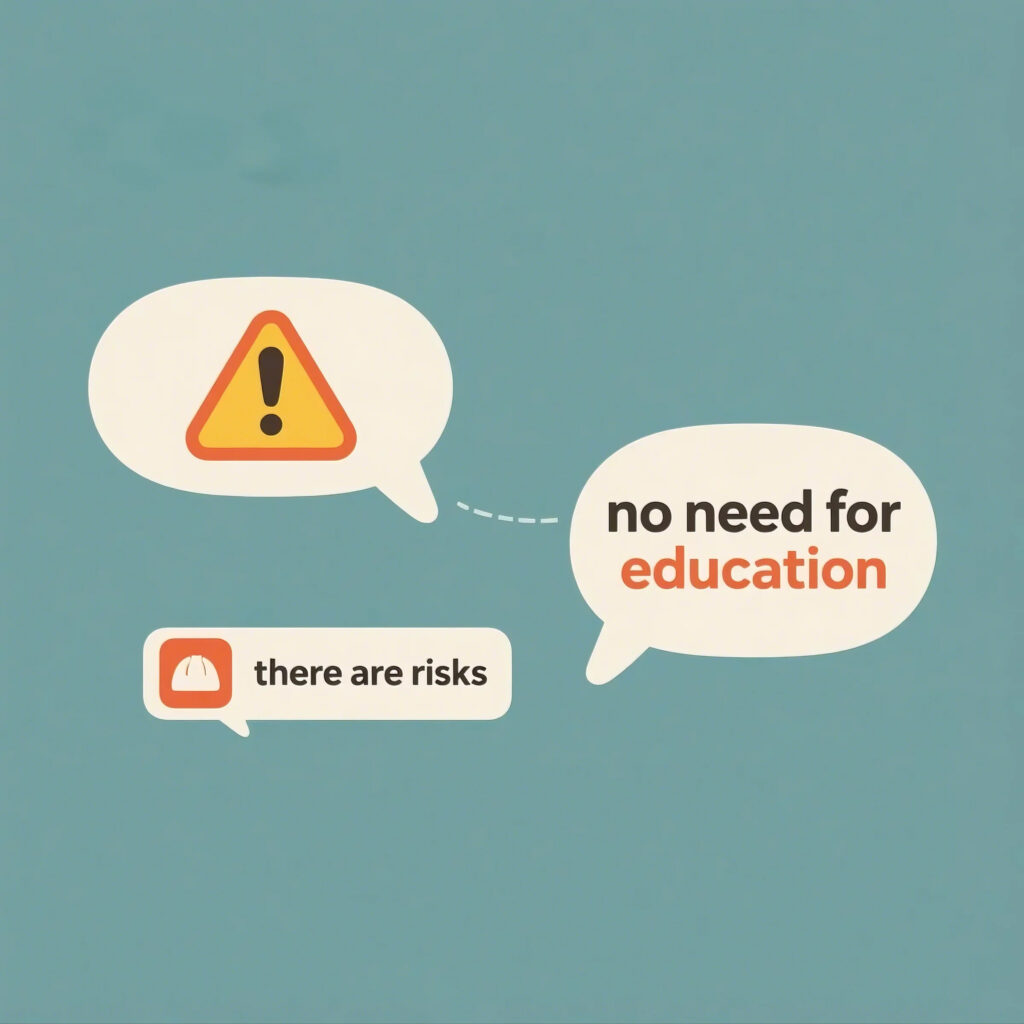
「金持ち父さん 貧乏父さん」は多くの気づきを与えてくれる一方で、誤解を招きやすい点もあります。
「学歴は不要」「会社員はダメ」という話ではない
本書では「学校で学んだことだけでは豊かになれない」と強調されていますが、これは「学校や会社は無意味」と言っているわけではありません。
学歴や安定した職業が悪いのではなく、「そこに依存しすぎることがリスク」だと警鐘を鳴らしているのです。
会社員として働きながら投資を学び、徐々に資産を築いていくことは十分に可能です。
むしろ、安定した収入があるうちにお金に働いてもらう仕組みを作るのが理想的なステップだと言えるでしょう。
リスクを取れば誰でも金持ちになれるわけではない
本書を読んで「すぐに投資を始めよう!」と考える人も多いですが、無計画に投資を始めると、かえって資産を失ってしまうリスクもあります。
キヨサキ氏が伝えたいのは、「まず学べ」ということです。
「不動産投資が儲かる」「株が上がりそう」といった噂に飛びつくのではなく
- リスクを正しく理解すること
- 小さく始めて経験を積むこと
- 継続的に学び、改善すること
このような姿勢が、お金に振り回されない本当の豊かさにつながります。
この本を読んだ感想と私の行動

資産と負債の違いについての理解
以前の私はお金に関する知識が乏しく、所謂マネーリテラシーの低い人間でした。
私自身、マイホームも車も所有しています。
もう購入してしまっているので、後悔はありませんが、資産形成を本気で考えるようになり、家計管理を始めるようになってから、これらが家計に与える負担の大きさを実感しました。
マイホームや車を否定するつもりはありませんが、購入を検討する際に、「資産と負債の違い」という視点を持っておくことで、選択肢を増やすことができるようになります。
インデックス投資の開始
本書を読んだのは2023年の年末ごろで、新NISAのスタートが控えている時期でした。
当時の私は投資の知識が全くなく、投資はギャンブルと同じようなものという認識。
しかし、本書を読んだのをきっかけに投資のことを勉強し、新NISAを活用してインデックス投資を始めました。
まだ不労所得とは呼べませんが、投資を始めたことで、少額でも「お金に働いてもらう」感覚を掴むことができました。
今後も継続して淡々と積み立て投資を行い、資産を増やせていければと思っています。
学び続けることの重要性とマネーリテラシーを上げること
マイホームや車の件でも述べましたが、私はかつてマネーリテラシーの低い人間でした。
しかし、このままでは一生お金に苦労すると思い、本やYOU TUBEでお金や簿記の勉強を始めたおかげで少しずつ、マネーリテラシーが上がってきたと感じています。
お金の勉強や簿記の知識は家計管理をする上で非常に役に立っていて、都度家計を見直し、収支の最適化ができるようになってきました。
本書にも書かれていた「学ばないことこそがリスクである」ということを身にしみて実感しています。
まとめ
お金に関する学びの第一歩としての一冊
『金持ち父さん貧乏父さん』は、「働き方」や「お金の使い方」に対する固定観念をくつがえし、私たちに「経済的自由」という新しいゴールを提示してくれる名著です。
本文中に難しい専門用語は使われておらず、初心者でもスッと読める内容となっています。
資産と負債の違いを知ること
お金に働いてもらう仕組みをつくること
学び続け、自分の頭で判断すること
こうした力は、これからの時代を生き抜く上で欠かせない武器となります。
もしあなたが今、お金に不安を感じているなら——
本書は、きっと人生の指針となってくれるはずです。
この一冊を通して、「お金についてを学ぶ」ことを取り入れてみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が参考になれば幸いです。